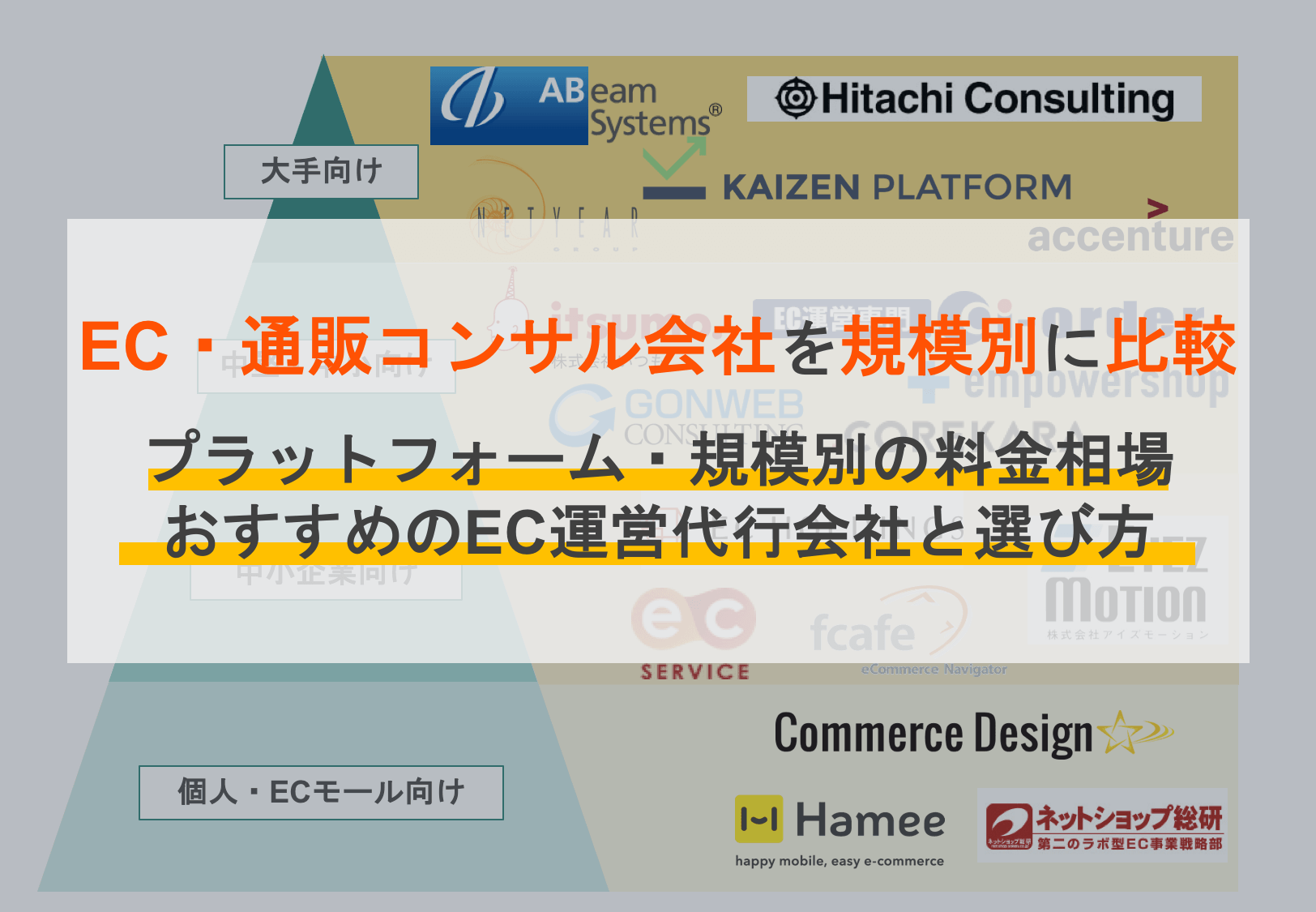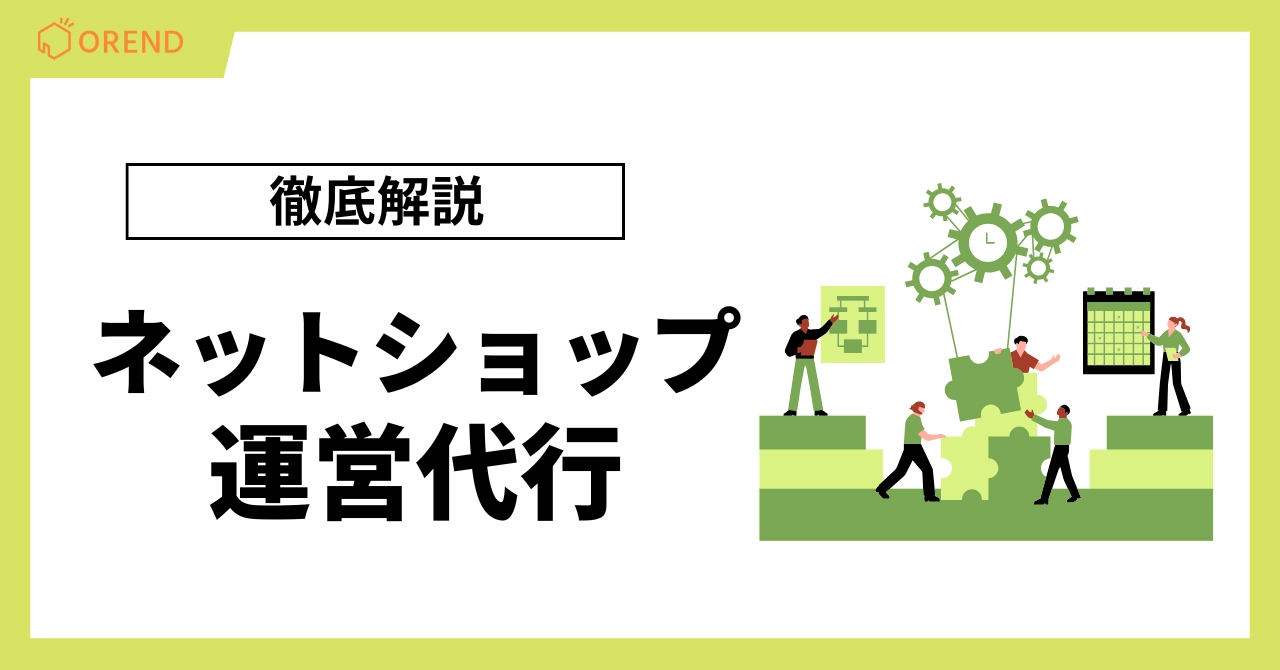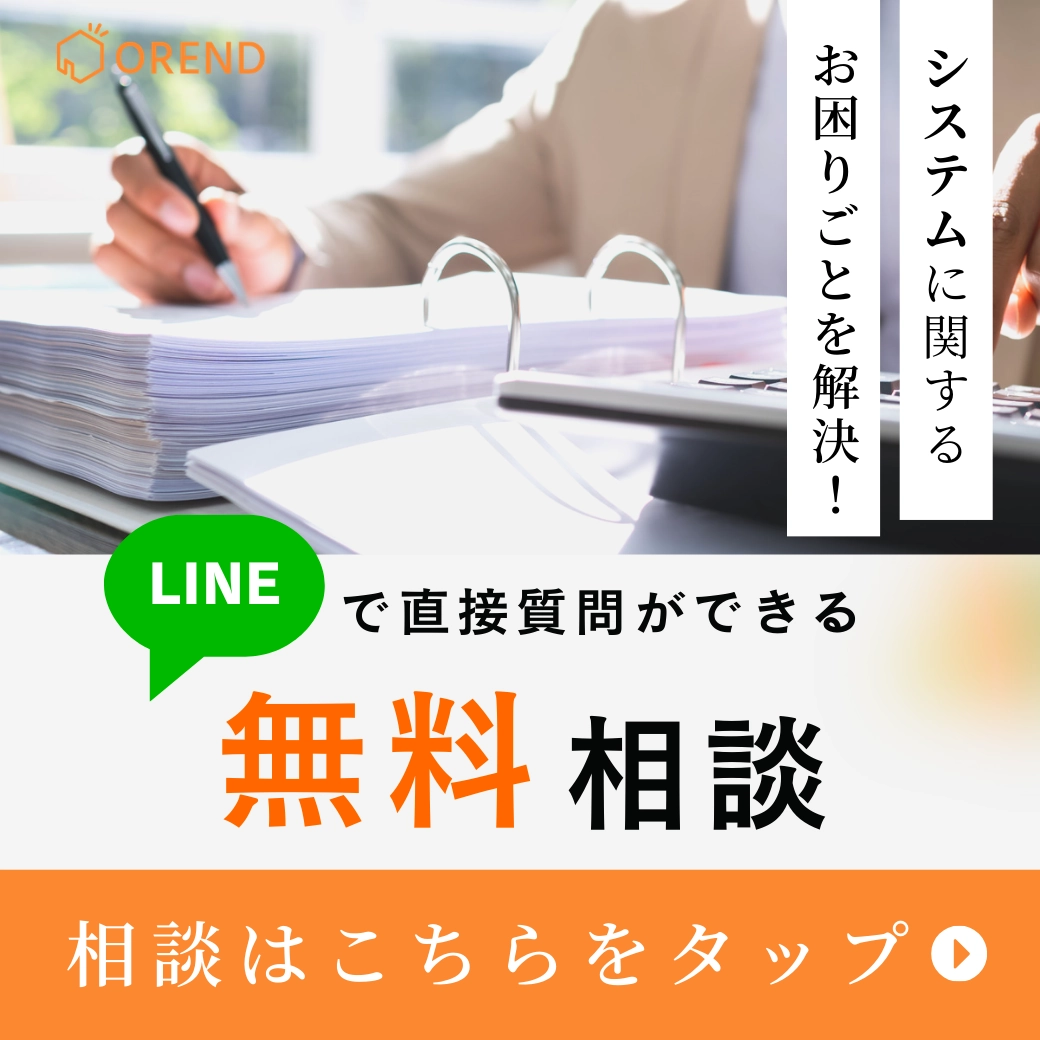- ECサイト運営の主な業務内容と必要なスキル
- ECサイト構築・運営でかかる費用
- 売上アップのためのEC戦略と改善ポイント
ECサイト運営とは?
ECサイト運営とは、ECサイトを通じて商品やサービスを販売し、継続的に売上を伸ばすための仕組みを構築・管理することです。
ECサイトは実店舗と異なり、サイトに訪れたユーザーが、商品を見つけ、購入し、商品が手元に届くまでのすべてがオンライン上で完結します。そのため、ECサイト運営にはリアル店舗以上に「システム」と「導線設計」の工夫が必要です。
ECサイトを運営するうえでは、次のようなことを考えながらサイトを改善していきます。
- ECサイトに訪問してもらう仕組みづくり
- 商品を魅力的に見せるページ設計
- 受注から発送までのスムーズな処理
- アフターフォローやリピート対策
つまりECサイト運営とは、「商品企画」から「販売・集客」、「配送・サポート」まで、オンライン販売全体を設計・改善する総合的な取り組みなのです。
フロント業務
ECサイトにおけるフロント業務とは、ユーザーが直接触れる部分の設計と運用を指します。
- 商品企画
- 仕入れ・製造
- 集客施策
- 分析・改善
フロント業務に求められるのは、「見せ方・伝え方・導き方」のスキルです。ECサイトで商品を買ってもらうには、魅力的な商品画像、わかりやすい説明、購入しやすい導線設計が欠かせません。
フロント業務が機能すると、ユーザーの興味を惹き、商品を「ほしい」から「買う」へと変えることができます。
バックエンド業務
バックエンド業務は、ユーザーには見えない部分でECサイト運営を支える重要な作業です。具体的には、以下のような業務が該当します。
- 受注処理
- 在庫管理
- 配送手配
- 問い合わせ対応
バックエンドの品質が低いと、商品が届くのが遅れたり問い合わせの対応が不十分になったりと、顧客の不満につながります。そのため、ECサイトの信頼性を守るうえで、バックエンド業務の効率化は不可欠です。
EC担当者の役割とは
EC担当者は、フロントとバックエンドの両面からECサイト運営をリードする役割を持ちます。売上データや顧客の行動を分析し、改善施策を実行しながらサイト全体を整えていきます。
EC担当者の仕事は単なるオペレーションではなく、売れるECサイトの仕組みを設計し、継続的に改善していく“戦略の実践者”と言えるでしょう。
ECサイト運営は、商品企画から販売・発送、アフターフォローまで、9つのステップで進められるケースが一般的です。これらは「フロント業務」と「バックエンド業務」に分類され、それぞれに役割があります。まずは全体の流れを理解し、各業務の関係性を整理しておくことが大切です。
ECサイト運営の作業フロー(9つのステップ)
フロントとバックエンドの視点で整理すると以下のようになります:
【フロント業務】=ユーザーに見える業務・売上をつくる業務
【バックエンド業務】=裏側で運営を支える業務・品質を守る業務
- 商品企画(フロント業務)
- 仕入れ・製造(フロント業務)
- 商品登録・サイト更新(バックエンド業務)
- 集客施策(フロント業務)
- 受注管理(バックエンド業務)
- 在庫管理(バックエンド業務)
- 梱包・配送(バックエンド業務)
- アフターフォロー(バックエンド業務)
- 分析・改善(フロント業務)
このように、フロント業務は「売れる流れを作る」、バックエンド業務は「売ったあとを支える」という役割を担っています。どちらか一方だけではECサイト運営は成り立たず、両方の業務が連携してこそ、顧客にとって快適な購買体験が実現します。
①商品企画(フロント業務)
商品企画はECサイト運営における最重要工程のひとつです。この段階でつまずくと、その後どれだけサイト改善を行っても売れる商品にはなりません。
実務としては、対象顧客像(ペルソナ)を明確にし、どんな課題や欲求を持っているのかを分析することからスタートします。そのうえで、コンセプト、価格帯、仕様、提供価値を設計し、競合との差別化を図ります。
商品企画で忘れてはいけないのは、「売りやすい商品」を作ることです。たとえば単価が高すぎる、使用シーンが限定的、すでに市場が飽和している商品などは、初動から苦戦しがちです。顧客価値と市場性のバランスを重視しながら設計しましょう。
②仕入れ・製造(フロント業務)
商品企画が固まれば、次は実際の仕入れ・製造工程に進みます。ここでは、商品供給の安定性と品質の担保が非常に重要です。供給が不安定だと、売れるタイミングを逃したり在庫切れを起こしたりして販売機会を失います。
製造委託の場合は、生産ロット・製造スケジュール・品質管理ポリシーなどを事前にすり合わせておくことが欠かせません。特に、初回製造ロットではサンプルを取り寄せ、問題がないかを確認したうえで本生産に移るのが鉄則です。
また、見落とされがちなポイントとして、パッケージングやラベル表示の法令順守があります。食品や化粧品、医薬部外品などは表示ルールが厳格で、違反すると販売停止になるリスクもあります。製造前の段階でしっかりチェックしましょう。
③商品登録・サイト更新(バックエンド業務)
商品登録は、ECサイトに商品を掲載して「売れる状態」にするための作業です。ここで重要なのは、商品情報を“ただ掲載する”のではなく、“売れるように見せる”ことです。
まず、商品画像はプロのカメラマンやスタジオを活用することで、クオリティが一気に向上します。予算が少なければ自然光を活用するなどの工夫も有効です。商品説明文は、スペックだけでなく、使用シーンやメリット、他社との差別化ポイントを明確に伝えることがポイントです。
また、登録後の更新体制の整備も重要です。販売状況やレビュー、ユーザーの行動データを分析し、必要に応じて商品ページを改善していくことで、検索流入を増やし、購入率を改善できます。効果的な商品ページとは、販売開始後も改善し続ける“育てるページ”です。
④集客施策(フロント業務)
集客施策は、売上を伸ばすための出発点です。最初にやるべきは、「誰に(顧客像)」「どこから(チャネル)」「どう届けるか(メッセージ)」を決めることです。
例えばSNS集客では、ターゲットが20代女性ならInstagram、ビジネス系ならX(旧Twitter)、調査検索が多い場合はSEO対策が有効です。施策ごとに効果測定(CTR・CVR・CPA)を行い、「売上につながるチャネル」に集中投資するのが鉄則です。
失敗するECにありがちなのが、「集客しているつもりで実は売れていない状態」。流入だけでなく商品ページでの購買導線改善も同時に取り組むのが成功のポイントです。
⑤受注管理(バックエンド業務)
受注管理は「売った後の信頼を守る業務」です。注文が入ったら、決済確認、在庫連携、発送手配までをミスなく迅速に処理する必要があります。
手動での対応には限界があるため、受注管理ツールやECシステムの自動化機能を活用するのがおすすめです(例:Shopify、futureshop、BASEなど)。メール通知やステータス管理の自動化により、ミス防止と業務効率アップが実現できます。
「決済済なのに発送が遅れる」「在庫ありなのにキャンセル対応」といったミスは、クレームや評価低下に直結するため、早期に仕組み化することが重要です。
⑥在庫管理(バックエンド業務)
在庫管理は適切に行わないと、売り逃し(在庫切れ)や資金拘束(過剰在庫)につながるリスク管理業務です。
売れ筋商品の需要予測をもとに、仕入れタイミング・数量を調整する仕組みが必要です。小規模ECでも「売り切れの多発」「在庫の山積み」といった状態はよく起こりがちで、データに基づく予測と定期確認が欠かせません。
また、倉庫やシステム連携が整っていない場合は、Excelでの在庫管理でも構いませんが、早期に「在庫自動同期ツール」への移行を検討すると、運用の安定化が図れます。
⑦梱包・配送(バックエンド業務)
梱包と配送は、ECサイトがお客様に与える最終印象を決める重要な業務です。きちんと梱包され、予定通りに届くことは当たり前と思われがちですが、これができないとクレームや低評価に直結します。
実務的には、商品に合わせた梱包材の選定、破損防止、伝票貼付、配送業者への連携といった流れが発生します。配送が遅れると、顧客に不信感を与え、リピーター獲得機会も失います。
梱包の質と配送スピードは差別化ポイントにもなるため、提携する配送業者の選定や倉庫の出荷体制改善に投資する価値は十分あります。
⑧アフターフォロー(バックエンド業務)
アフターフォローは、リピーター化と顧客満足度向上に直結するフェーズです。問い合わせ対応や返品処理、レビュー依頼などを通じて「また買いたい」と思ってもらえる体験を提供します。
たとえば、商品到着後に自動フォローメールを送って使い方情報を案内したり、レビュー投稿依頼をすることで、自然なコミュニケーションが生まれます。問い合わせへの対応が雑だと、せっかくの顧客も離れてしまうため、対応の速さ・丁寧さが肝となります。
アフターフォローは、売上を伸ばす“縁の下の力持ち”であり、改善するとリピート率に明確な差が出ます。
⑨分析・改善(フロント業務)
分析・改善はECサイト運営において、売上を伸ばし続けるための根幹業務です。アクセス数、コンバージョン率、客単価などの数値を定期的に確認し、課題を特定して改善策に落とし込みます。
たとえば「アクセスはあるのに売れていない」と分かった場合、商品ページの情報不足や、購入導線の改善が必要かもしれません。改善案を試して、効果を検証し、成果が出たら他商品にも展開する、という流れで運用していきます。
分析はGoogle Analytics、Search Console、EC管理画面のレポートなどのデータツールの活用が基本。継続的に改善を回せるEC担当者が、強いサイトを作り上げていきます。
ECサイト構築・運営に必要な費用と相場
ECサイトを始めるうえで、構築費用・運営費用・広告費用といったコストは欠かせません。ここでは、代表的なECサイトのタイプ別に費用相場を分かりやすく整理し、自社に合う方法を選ぶための判断基準を紹介します。
ECサイトのタイプ別|初期費用と月額費用の比較
ECサイトの構築には大きく分けて4つのタイプがあります。それぞれに特徴とコスト構造が異なるため、販売規模や機能要件に応じて選ぶことが重要です。
| サイトタイプ | 初期費用 | 月額費用 | 特徴 |
| モール型 (Amazon、楽天市場など) | 0〜50万円 | 5万〜30万円 +手数料 | 集客力は高いが手数料負担あり |
| ASP型 (Shopify・BASE・STORES) | 0〜20万円 | 0〜3万円 +決済手数料 | 小規模〜中規模向け。構築が簡単 |
| パッケージ型 (futureshop・MakeShopなど) | 50〜200万円 | 5万〜20万円 | カスタマイズ性が高く拡張にも向く |
| フルスクラッチ (自社開発) | 300万円以上 | 10万〜100万円 ※保守費用含む | 大規模EC・独自要件向け |
選び方のポイント
- 小〜中規模のEC初心者には、初期費用を抑えて始められるASP型がおすすめ
- 年商1億円以上を狙う場合は、拡張性の高いパッケージ型や、自社開発を検討する余地あり
- モール型は集客メリットがある一方、手数料が高いため自社ECとの併用戦略が一般的

ECサイト運営で発生する費用の内訳
構築後も、ECサイトの運営には継続的にコストがかかります。以下が主な項目とその費用目安です。
| 費用項目 | 費用目安 | 内容例 |
| 広告費 (リスティング/SNS広告など) | 月1万〜100万円 | 新規顧客獲得のための投資 |
| 商品撮影・制作費 | 1商品あたり数千円〜5万円 | 商品の魅力を伝える画像・動画制作 |
| 受注・在庫管理ツール | 月数千円〜数万円 | EC運営の自動化・効率化 |
| 物流費 (梱包・配送) | 1件あたり約300円〜1,500円 | 発送コスト、倉庫保管費用 |
| 人件費 (内製/外注) | 月10万〜50万円 | 商品登録・カスタマーサポートなど |
ECサイト費用を抑えるコツ
- 無料〜低コストのECカートでスタート
ShopifyやBASEなら、初期投資を最小限に抑えつつ運用開始可能。 - 広告は小額からテストして最適化
初期から大きく投資せず、少額でCPAを見極めながら改善を回す。 - 内製と外注のバランス設計
画像撮影や商品登録など、外注より社内で対応可能な作業は内製化する。
ECサイト運営は「どこにお金をかけ、どこで抑えるか」の戦略設計が重要です。費用対効果を意識しつつ、自社に最適なサイト構造・運営体制をつくることが成功の第一歩となります。
ECサイト運営に必要なスキル
ECサイトの運営には、「売る人」としての視点と、「支える人」としての視点の両方が求められます。ここでは、実務に必要な4つの主要スキルを解説します。
Webマーケティング(SEO・広告・SNS運用)
ECサイトの成功は、集客ができるかどうかがカギです。中でもWebマーケティングの知識はEC担当者の必須スキルと言えます。
- SEOで商品の検索流入を増やす
- Google広告やInstagram広告で新規顧客を獲得
- SNS投稿でブランドのファンを育てる
施策ごとの効果測定(CTR、CVR、CPAなど)ができると、「何が売上につながっているか」が分かり、効果的な施策に集中できるようになります。
商品企画スキル
どれだけうまくサイトを構築しても、売れる商品がなければ意味がありません。商品企画では以下の力が問われます。
- ターゲット顧客のインサイト把握
- 他社との差別化要素の設計
- 売れるスペック・価格設定
リサーチ力とクリエイティブな発想で、「売れる商品を用意できるかどうか」がECサイトの収益性を大きく左右します。
クリエイティブ制作スキル
ECサイトでは商品の魅力が「画面上だけ」で決まります。そのため、商品画像や説明文のクオリティが売上を大きく左右します。
- 魅力を伝える商品画像の撮影・加工
- 読みやすく訴求力のある説明文作成
- ランディングページ(LP)の設計
制作が外注の場合でも、EC担当者として「何を伝えるべきか」を設計できる力が重要です。
カスタマーサポートスキル
顧客とのやり取りを適切に行い、快適な購買体験を提供することは信頼を生むために欠かせません。
- 問い合わせ対応の迅速さと丁寧さ
- トラブル時の対応マニュアル整備
- レビュー対応やフォローアップ
顧客の不満を放置すると、リピート率の低下や悪レビューにつながります。顧客心理に寄り添う対応ができる運営体制が売上の安定に直結します。
ECサイトの売上アップのための戦略と施策
ECサイト運営で売上を伸ばすには、単に商品を並べるだけでは不十分です。「誰に」「何を」「どのように届けるか」を戦略的に設計し、施策を継続的に改善することが重要です。
ECで売れる商品コンセプト設計
まず売上を伸ばすためには、明確で共感される商品コンセプトが必要です。
- 誰に届ける商品なのか(ターゲットの設定)
- 顧客の悩みや欲求にどう応えるのか
- 他社商品との違いやメリット
たとえば「忙しい人向けの時短スキンケア」「ギフト需要に特化したスイーツ」など、明確な切り口を持つことで、ユーザーに響く商品として選ばれやすくなります。
集客から購入までの導線設計
ECサイトに集客しても、購入に至らなければ意味がありません。購入までの導線を設計することで、CVR(コンバージョン率)の改善が期待できます。
- アクセスしてすぐ商品の魅力が分かるページ構成
- レビュー・口コミの掲載で安心感を提供
- カートに商品を入れやすいUI設計
また、サイト内だけでなく、SNSや広告経由でも自然な遷移を設計し、各タッチポイントでの一致したメッセージを届けることも効果的です。
リピートしてもらうための仕組みを設計
新規顧客獲得よりも、既存顧客のリピート率を上げるほうが低コストかつ効果的です。以下のような仕組みを導入することで、ファンづくりにつながります。
- 配送後のサンクスメールや次回クーポン
- 定期購入プランの導入
- LINEやメルマガでの情報配信
顧客との継続的なコミュニケーションを取ることで、LTV(顧客生涯価値)を高め、売上の安定につなげることができます。
ECサイト運営の課題と改善ポイント
ECサイトを継続的に運営していくと、売上や業務効率の面でさまざまな課題に直面します。ここでは、特に重要な3つの課題と改善策を解説します。
商品ページとサイト構成の見直し
商品の魅力が十分に伝わっていなければ、サイト流入があっても購入にはつながりません。商品ページを改善することは売上改善の最優先事項です。
- 商品画像や説明文の質を改善する
- スマホ対応のレイアウトでユーザビリティ向上
- 関連商品をレコメンドして客単価アップ
具体的には、画像を「引き」「寄り」「使用シーン」と複数用意し、顧客が想像しやすい状態にしておくことが効果的です。
物流・配送プロセスの無駄の削減
発送遅延や梱包ミスは、顧客満足度の低下につながります。物流フローの見直しは顧客満足とコスト削減の両方につながる改善ポイントです。
- ピッキング〜梱包〜発送の手順を標準化
- 外部物流サービス(3PL)の活用で負担軽減
- 配送会社ごとの特徴を活かした最適化
特に「受注後にすぐに発送する体制が整っているか」がリピーター獲得に大きな影響を与えます。
カスタマーサポート強化
商品に対して満足していても、問い合わせ対応の遅さで購入をやめるケースは多いです。
- チャットボットやFAQでセルフ解決を促す
- 定型返答だけでなく、顧客に寄り添った対応
- クレーム対応マニュアルの定期改善
問い合わせ対応が改善されることで、レビュー評価の向上や再購入率アップという効果も期待できます。
ECサイト運営と実店舗運営の違い
ECサイトと実店舗では運営方法に大きな違いがあります。まず注目すべきは、集客手段です。実店舗は立地が集客の決め手となる一方で、ECサイトはSEOや広告、SNSにより全国からユーザーを集められるという特徴があります。言い換えれば、良い場所に店舗を構える代わりに、サイトやコンテンツを最適化する必要があるのです。
次に、顧客とのコミュニケーションも異なります。実店舗では対面接客が基本となり、表情や声のトーンから顧客の心理を読み取れます。一方、ECではテキストや自動応答が中心となるため、いかに分かりやすく安心感を与えるかが鍵となります。FAQの充実や丁寧なメール対応が信頼構築につながります。
以下の比較表で、両者の特徴を整理してみましょう。
| 項目 | ECサイト運営 | 実店舗運営 |
| 集客手段 | SEO・広告・SNSなどWeb施策中心 | 店舗の立地や商圏が鍵 |
| 営業時間 | 24時間いつでも購入できる | 営業時間内に限定 |
| 顧客対応 | メール・チャット・FAQで対応 | 対面でリアルタイム対応 |
| 購買体験 | テキスト・画像で判断 | 実物に触れて納得して購入 |
| 運営コスト | 初期費用を抑えやすい | 賃料・人件費が高く付きやすい |
| データ活用 | アクセス数・CVR等を数値で可視化可能 | 感覚や経験に頼る場面が多い |
ECのメリットは「低コスト」「データに基づいた改善」「時間や地域に縛られない販売」などが挙げられます。一方で、商品を直接体験できないという弱点を補う工夫が必要になります。
つまり、ECで売上を伸ばすには、魅力が伝わる商品ページづくり・信頼を感じさせるサポート・スムーズな配送体制など、サイト全体でリアルに負けない体験を設計していくことが不可欠なのです。
自社に合ったECシステム・サービスの選び方
ECサイトを構築・運営する際に最も重要な要素のひとつが、どのECシステム(カート)を選ぶかという点です。この選択によって、運用負荷や費用、機能の拡張性が大きく変わります。
ECシステムには、代表的に「モール型」「ASP型」「パッケージ型」「フルスクラッチ型」の4タイプがあります。それぞれの特性を理解し、自社の商品特性や販売規模に合ったものを選ぶことが重要です。
たとえば、初期費用を抑えてすぐに販売を開始したいなら、ShopifyやBASEなどのASP型が向いています。管理画面も分かりやすく、商品登録やデザイン変更も簡単に行えます。反対に、独自のカスタマイズをしたい、自社システムとも連携したい、というニーズがある場合は、MakeShopやfutureshopといったパッケージ型や、フルスクラッチでの構築を検討する必要があります。
以下に主要なECシステムの比較表をまとめます。
| システムタイプ | 初期費用 | 運用費用 | 特徴 |
| モール型 | 低コスト | 手数料高め | 集客力が高い。楽天やYahoo!など |
| ASP型 | 無料〜数十万円 | 月額〜数万円+手数料 | 初心者向け。Shopify、BASEなど |
| パッケージ型 | 50万〜200万円 | 月数万円〜 | 柔軟なカスタマイズ。MakeShopなど |
| フルスクラッチ型 | 数百万円〜 | 保守費用高め | 自由度最高。大規模EC向け |
システム選定で失敗しないためには、今の事業フェーズに合った規模・機能を選ぶことが大切です。「売上が伸びたら乗り換えればいい」といった割り切りもアリですが、移行時にはデータ移管や費用が発生するので、予め想定しておきましょう。
ECカートはただの“箱”ではなく、ビジネス全体を支える“基盤”です。費用と機能、運用のしやすさ、拡張性、そしてサポート体制をバランスよく見極めて、自社に合ったシステムを選びましょう。
まとめ
ECサイト運営は、多岐にわたる業務をバランスよく行うことが求められる仕事です。商品企画から集客、受注管理、顧客対応、分析・改善まで、一つ一つの積み重ねが売上の成長に直結します。
特に、成果につながるためのポイントは次の3つです。
- 売れる商品とユーザー目線のコンテンツ設計 ターゲットを絞り、魅力が伝わる商品ページを作ることで、CVRを高められます。
- 導線設計とリピート対策で売上を伸ばす 集客だけでなく、購入までの流れと購入後のフォローを丁寧に行うことで、長期的な売上安定が実現します。
- ECシステム選びが運営体制を左右する ASP型・モール・パッケージなど、自社の規模や戦略に合わせた選択が重要です。
ECサイト運営は、数字が明確に見えるからこそ改善サイクルを回しやすいビジネスです。小さな成功体験を積み重ねながら、自社ならではの強みを武器に、着実な成長を目指しましょう。
この記事にはタグがありません。